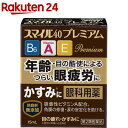テレビが私たちの“情報源”であり続ける理由
情報過多の現代。けれども私たち60代、70代にとって、一番信頼して頼りにしている情報源は、やっぱり**「テレビ」**ではないでしょうか。最近、NTTドコモ モバイル社会研究所の調査で、私たちの世代が生活情報を得るメディアとしてテレビが最も多いという結果が出たと聞き、「納得の結果でした」と思わずうなずきました。
テレビはただの娯楽ではなく、生活に直結した情報の宝庫でもあります。では、なぜここまで根強くテレビが支持されているのでしょうか。その背景には、私たちの生活スタイルや価値観、そして社会の変化が密接に関わっています。
◆>>【めぐみのルテイン30】ルテインで視界クッキリ!※目のぼやけ、かすみ、疲労感【送料無料】テレビの安心感と信頼性

- 長年親しんできた媒体である
- 映像と音で分かりやすい
- ニュースや生活情報が網羅的
- 信頼できるアナウンサーや専門家の解説
新聞やネットももちろん情報源として活用されている方は多いと思いますが、テレビの安心感というのはちょっと特別です。自宅でくつろぎながら、映像と音声で「生きた情報」を受け取れるのは、まさにテレビならではの強みです。文字だけの情報では伝わりにくい感情や状況が、映像を通してよりリアルに感じ取れるため、理解が深まりやすくなります。
たとえば、地震や台風といった自然災害の速報をテレビで知ったとき、その緊迫した映像とキャスターの真剣な語り口によって、情報の重要性が一気に伝わってくることがあります。こうしたとき、画面越しにでも人の声が聞こえてくると「ひとりじゃない」と感じられ、安心できるのです。
また、テレビは番組全体の構成が考えられているため、テーマに沿って自然な流れで情報が入ってきます。CMで一息つけるのも、私たちにはちょうどいいリズムかもしれませんね。最近では字幕放送も増えており、耳が遠くなってきた方でも安心して内容を理解できます。
さらに、信頼できるアナウンサーや長年見てきた番組という存在は、いわば「顔なじみ」のような感覚すら生んでいます。毎朝決まった時間にニュース番組を観るという習慣は、生活リズムを整える助けにもなっています。
特に災害時や緊急時の速報など、信頼できるアナウンサーの声を聞くだけでホッとした経験、皆さんにもあるのではないでしょうか。テレビは情報と同時に「安心感」や「落ち着き」まで届けてくれる、そんな存在だと改めて感じています。
スマホは便利、でも目が疲れる?
- スマホやパソコンの長時間利用は目に負担
- 小さい画面は見づらい
- 誤操作が起こりやすい
- 使い方が難しいと感じることも
私も最近ようやくスマートフォンを使い始めました。確かに便利ではありますが、どうしても「小さい文字」「眩しさ」に苦労しています。触ってみたものの、やはりテレビの方が楽でした。画面が大きく、操作も不要。受け身でいられるって、実は大きな魅力なんですよね。
40〜50代は「Web・アプリ」派
- パソコン世代としての親和性
- 検索スキルが高い
- 時間に追われて効率重視
- スマート家電との連動も活用
子ども世代、あるいは職場で関わる40代・50代の方々を見ていると、ウェブサイトやアプリをサクサク使いこなしていて感心します。調べたいことはすぐ検索、電車の遅延もスマホで確認。私たちの世代からすると「なんだか急いでるなぁ」と感じることも。でもそれが、現役世代にとっての“日常”なのでしょうね。
若い世代はSNS中心
- 情報のスピードが命
- 友人やインフルエンサーからの情報を重視
- 写真や動画で直感的に受け取る
- テレビより「双方向性」が重要
私の孫もスマホ片手にTikTokやInstagramを見ていますが、正直、まだ馴染めません。でも彼らはそこからファッションや料理、ニュースまで、あらゆる情報を仕入れているようです。私たちがテレビに感じる“信頼感”を、彼らはSNSに感じているのかもしれません。
グラフで見る世代別メディア利用傾向

| 世代 | 主な情報源 |
|---|---|
| 10〜30代 | SNS(Instagram、X、TikTokなど) |
| 40〜50代 | Web・アプリ(Yahoo!ニュース、新聞アプリなど) |
| 60〜70代 | テレビ(地上波、BSなど) |
(出典:NTTドコモ モバイル社会研究所)
この表を見ても、世代ごとの明確な傾向が浮き彫りになりますね。特に注目すべきは、それぞれの世代が「何を重視して情報を選んでいるか」の違いです。
たとえば若い世代は、情報のスピード感とリアルタイム性を最も重視しています。SNSで話題になったことが、数分後にはトレンドになっている世界です。自分の興味のあるテーマをフォローしておけば、自然と情報が入ってくる仕組みも彼らにとって魅力的なのだと思います。
一方で40〜50代になると、「正確性」や「信頼できる出所」が気になってきます。会社や家庭の責任を担う立場になると、誤った情報に振り回されるわけにはいきません。そうなると、ニュースアプリや新聞社のWeb版など、裏付けがしっかりしたメディアを好む傾向にあるようです。
そして、私たち60代・70代が大切にするのは「分かりやすさ」と「親しみ」です。テレビは映像と音声を通じて感覚的に理解できるので、読み取る力や操作力をそれほど必要としません。リモコンひとつで得られる安心感と直感的な理解のしやすさは、他のメディアにはない魅力だと思います。
情報の信頼性・スピード・使いやすさなど、何を重視するかによって、自然と選ばれるメディアは異なってきます。それは単なる好みの違いではなく、世代ごとの生活環境や経験、さらには技術との関わり方が生んだ必然の流れとも言えるでしょう。
こうしてみると、情報をどこから得るかという行動そのものが、私たちの生き方や価値観を映し出す鏡のようにも思えてきます。
テレビが担う役割の変化
- エンタメだけでなく生活密着型へ
- 医療・健康・防災情報が豊富
- 地域情報にも強い
- 高齢者向け番組の充実
昔のテレビといえば、ドラマやバラエティ中心でしたが、今は健康番組や生活情報が豊富になりましたよね。例えば「ためしてガッテン」や「世界一受けたい授業」など、年齢を重ねると関心が強くなるテーマに寄り添ってくれている番組がたくさんあります。
デジタル化で生まれる“情報格差”

- スマホ利用が難しい高齢者は情報から取り残されやすい
- 行政や病院もWebでの案内が増えている
- 家族のサポートが不可欠
- アナログ媒体の必要性も再認識
実際、区役所からの通知が「Web確認のみ」なんてことも増えました。私は印刷してくれた紙が一番助かります(笑)。文字を読むだけでなく、すぐに手元に残る安心感があるからです。
さらに、病院の予約や公共施設の利用案内なども、最近は「スマホアプリでご確認ください」と書かれていることが多くなりました。けれど、そのアプリをダウンロードするにはIDやパスワードの登録が必要で、途中でつまずいてしまったことも。結局、電話で確認して済ませたのですが、デジタルが主流になることで「わからない人は置いていかれる」空気を感じる瞬間が確かに増えてきました。
例えば私の友人で、長年ガラケーを使っていた方がいましたが、スマホへの買い替えを強く勧められて仕方なく変更。その後、LINEの設定がわからず、孫からの連絡を受け取れずに寂しい思いをしたという話も聞きました。これは決して他人事ではなく、私たち全員が直面しうる課題です。
この“情報格差”を埋めるためには、家族や地域の助け合いが必要不可欠です。たとえば、定期的に開かれている「スマホ教室」や「デジタル相談会」に参加するのもひとつの手ですし、子や孫に手ほどきを頼むのも良いことだと思います。恥ずかしがらず、わからないことを「わからない」と言える環境が、今こそ求められています。
そして同時に、テレビのように分かりやすく、誰もがアクセスしやすいメディアの価値も、改めて見直されるべきです。私たちにとってテレビは、ただの娯楽ではなく、生活のガイドであり、安心を届けてくれる存在なのです。
私の小さな失敗談:スマホでの迷子事件
先日、散歩中にスマホの地図アプリを使ってみたのですが、思った方向と逆に進んでしまい、結局30分以上もウロウロするはめに。途中で電池も切れてしまい、結局近くの交番に助けを求めました。やっぱり**「使い慣れていない道具」には落とし穴がある**と痛感した出来事でした。
さらに別の日、レシピアプリを見ながら夕飯の準備をしていたところ、広告を誤ってタップしてしまい、レシピが消えて焦ってしまったことも。慌てて戻そうとしたら、どこを押しても違う画面ばかりが開き、結局、レシピは諦めて冷蔵庫の中の材料で適当に済ませました。こういった経験からも、やはりテレビや紙の本には「迷わずに情報を得られる」という安心感があると実感しています。
情報の“質”を見極める力が大事に
- フェイクニュースや偏った情報に注意
- 番組の制作背景も意識
- 専門家の意見は必ず確認
- 情報を鵜呑みにしない姿勢
どんなメディアでも、受け取る側の「目」が試される時代です。テレビだからといって全部が正しいわけではありませんし、SNSも意外と役立つことがあります。大切なのは、“見極める力”を持つこと。これは年齢に関係なく、誰にとっても必要な力です。
世代を超えて伝えたいこと
- 情報の受け取り方に“正解”はない
- 自分に合った方法を大事にする
- 若い人から学ぶ姿勢も必要
- 知ることで生活の質が上がる
大切なのは、「知らない」ことを恥じないことだと思います。若い人たちがどんな方法で情報を得ているのかを聞くだけでも、新しい世界が見えてくるものです。逆に、私たちがテレビから得た深い知識を伝えることで、若い人たちにも新しい気づきを与えられるかもしれません。
まとめ:今の自分に合った“情報の窓口”を持とう
時代は変わっても、大切なのは「自分に合った情報の受け取り方」を持つことです。テレビでも、スマホでも、新聞でも――それぞれの良さがあります。
あなたは、どんな方法で情報を得ていますか?
もし最近、「情報に追いつけていないかも」と感じているなら、まずはテレビの情報番組やニュースを活用してみてください。そして、少しずつスマホやアプリにも触れてみると、新たな発見があるかもしれません。
まずは一歩踏み出してみることが大切です。これからも、自分に合ったメディアとの付き合い方を見つけていきましょう。
今日から、自分らしい“情報の受け取り方”を意識して、日々の生活をもっと豊かにしていきましょう。