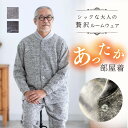60代世帯が頼りにする「生活資金源」のリアル――これからの安心のために
「60歳を過ぎてからの暮らし、資金のやりくり、どうしていますか?」
私自身、定年を迎えた時にふと感じたのは「これからの生活、どんな収入をあてにしていけばいいのだろう」という漠然とした不安でした。長年勤め上げてきた職場を離れ、公的年金を頼りに…と考えていたものの、思ったほど「年金だけじゃ心もとない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、金融経済教育推進機構の2024年調査結果をもとに、「今どきの60代世帯は、実際どんな資金源で暮らしているのか?」を、実体験や周囲のエピソードを交えて分かりやすくご紹介します。
同じ60代のあなたに、「自分だったらどうしよう?」と考えながら、安心と納得のヒントを持ち帰っていただけたらうれしいです。
公的年金はやっぱり生活の柱

- 圧倒的多数が年金を生活のメイン資金に
- 年金だけで暮らす難しさを感じる声も
- 年金額や受給タイミングの違いに注意
私も多くの友人も、公的年金はやはり生活の“柱”です。単身世帯の8割以上、夫婦世帯でも約8割が年金を頼りにしています。とはいえ「思ったより少ない」「生活に余裕はない」という声もしばしば耳にします。
私自身、65歳からの年金受給を前に「繰り上げ受給」や「繰り下げ受給」で迷った経験もあります。年金額は人それぞれですが、60代に入ったばかりの頃は「まだまだ働きたい」と感じていましたし、実際年金だけで悠々自適とはいかない現実もあります。
年金の種類や受給額、タイミングをしっかり理解しておくことが、安心への第一歩だと痛感しています。
就業収入――まだまだ現役!働き続ける60代
- 就業収入を得ている人は意外と多い
- 夫婦世帯では共働きも珍しくない
- 働く理由は「生活費」「社会とのつながり」などさまざま
60代といえば「悠々自適」なイメージがありますが、就業収入を得ている人も3~4割と意外に多いのが実態です。特に夫婦世帯では、共働きで家計を支えているケースも増えています。
私の友人も、年金だけでは足りないと感じてパートを始めたり、シニア向けの再就職支援を利用したりと、「もうひと働き」している人がたくさんいます。
もちろん、生活費の足しにというのもありますが、「社会とのつながりを持ち続けたい」「健康のために動きたい」といった前向きな理由もよく耳にします。働くことが生きがいにつながるのは、年齢を重ねた今だからこそ強く感じるものです。
金融資産の取り崩し――“貯金”は安心の備え?
- 金融資産を取り崩して生活費に充てる人も多い
- どのタイミングで取り崩すか悩みがち
- 「いつまで持つか?」という不安も
60代のリアルな悩みのひとつが、「貯金はどれくらい残せば安心か?」というもの。調査では単身世帯の3割強、夫婦世帯の2割超が“金融資産を取り崩しながら”暮らしているという結果でした。
私自身も「これまでコツコツ貯めてきたお金を、どこでどれだけ使えばいいのか?」という悩みをよく感じます。「万が一の時の備え」と「今の生活費」どちらを優先すべきか――なかなか判断が難しいですよね。
自分に合った資産の使い方、ぜひ早いうちから考えておきたいものです。
表:60代世帯が頼りにする生活資金源(単身・二人以上世帯)
| 資金源 | 単身世帯(%) | 二人以上世帯(%) |
|---|---|---|
| 公的年金 | 83.2 | 79.8 |
| 就業による収入 | 35.4 | 41.6 |
| 金融資産の取り崩し | 34.3 | 22.3 |
| 企業年金・個人年金・保険金 | 14.7 | 18.2 |
| 利子・配当所得 | 7.7 | 8.1 |
| 家族・親族からの仕送り・援助 | 3.2 | 2.1 |
企業年金・個人年金・保険金――「プラスα」の安心
- 企業年金・個人年金があると大きな安心感
- 自分で加入していた年金や保険が頼りになる
- 企業年金の有無で老後の余裕に差が
現役時代に「企業年金」や「個人年金」に加入していた方は、やはり心強いという声が多いです。私の知人も、定年後に「個人年金の受け取りが始まって本当に助かった」と話していました。
一方で、企業年金がない方は、「もう少し備えておけばよかった」と感じることも多いようです。
「今からでもできる老後資金の備え」があるなら、何かひとつでも始めておくのが安心です。
利子・配当所得――資産運用で広がる選択肢
- 預金利子や株式配当など資産運用で得る収入
- 年々重要性が増している
- 資産運用初心者でも始めやすい商品も
最近は「資産運用で生活費を補う」シニアが増えています。私も少額から投資信託を始めてみました。昔ほど「投資は怖い」というイメージも薄れつつありますね。
周囲でも「定期預金の利子は少ないけど、配当金が結構うれしい」という声をよく聞きます。投資は難しそうに思えますが、最近はシニア向けの分かりやすい商品も登場しているので、興味があれば一度相談してみるのもおすすめです。
家族・親族からの仕送りや援助――“つながり”も資金源
- 家族からの援助に頼るケースも一定数存在
- 緊急時や病気のときは心強い
- 感謝の気持ちと気兼ねのバランス
「いざという時、家族や親戚から助けてもらった」という話も珍しくありません。私も一度、体調を崩した際に息子夫婦が食材を届けてくれて、とても助かりました。
普段は頼らなくても、“困った時のセーフティーネット”として家族の存在はとても大きいと感じます。ただし、甘えすぎないよう気をつけるのも大切ですね。
地域や自治体の支援――知っておきたい公的サポート
- 介護保険や高齢者向け福祉サービスの活用
- 自治体独自の補助や給付金も
- 情報収集の大切さ
私たち60代以降の暮らしを支えてくれるのは年金だけではありません。自治体によっては高齢者向けの独自サポートや、医療費の補助などが用意されていることも。
私も自治体の「見守りサービス」を利用して、安心感がぐんと増しました。「知らなかった!」で損をしないよう、日頃から情報収集しておくことが大切ですね。
持ち家・不動産の活用――住まいも資金源になる
- リバースモーゲージや賃貸収入で現金化
- 持ち家の売却でまとまった資金を確保
- 住み慣れた家をどう活用するか考える
「持ち家は資産」とよく言われます。リバースモーゲージ(自宅を担保にお金を借りる仕組み)や、空き部屋の賃貸で収入を得ているシニアも増えています。
私の近所でも、子どもが独立したあとの部屋を賃貸に出し、月々の生活費に充てているご夫婦がいます。「今の家をどう活かすか」も老後の資金源として、選択肢の一つといえるでしょう。
生活コストの見直し――「支出を減らす」も立派な資金管理
- 生活費の節約で“貯める”から“使い方”へ
- 定年後こそ固定費の見直しを
- 節約でも「楽しさ」を忘れずに
資金源を増やすだけでなく、「使い方の見直し」も老後の安心に直結します。私自身、定年後は携帯電話のプランや光熱費の見直しをして、毎月数千円の節約につながりました。
とはいえ、「節約=我慢」では続きません。たまには自分へのご褒美や、趣味にお金を使うのも大事です。上手な家計管理で、毎日をより豊かにしたいですね。
グラフ:60代世帯の資金源別依存度(イメージ)
plaintextコピーする編集する公的年金 ┃■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 83%
就業収入 ┃■■■■■■■■■ 35%
金融資産取崩し ┃■■■■■■■■ 34%
企業年金・個人年金 ┃■■■ 15%
利子配当 ┃■■ 8%
家族援助 ┃ 3%
これからの60代、あなたの「安心」の形は?
- 資金源の“組み合わせ”で安心感が生まれる
- どの資金源も「頼り方」は自分次第
- ライフプランを定期的に見直すことの大切さ
調査データを見ても分かるように、「年金一本」では心もとない時代です。複数の資金源を上手に組み合わせて、安心感を高めていくのが理想です。
私も定期的に「今の家計で大丈夫か?」を見直すようにしています。大切なのは、「どれを選ぶか」ではなく「どう組み合わせて活かしていくか」。一人ひとりに合った“安心の形”を探していきたいですね。
まとめ――これからの60代、今日からできる資金管理を
最後までお読みいただき、ありがとうございました。60代の生活資金源は、公的年金を中心に多様化しています。
「自分には関係ない」と思わず、できることからひとつずつ始めてみませんか?
例えば、家計簿をつけてみる、資産運用のセミナーをのぞいてみる、自治体のサポート情報を調べてみる――どんな小さなことでも、未来の安心につながります。
「この先も、自分らしく豊かな暮らしを送りたい」――そう願うあなたのために、このブログが少しでも参考になれば幸いです。
あなたは、どんな資金源を一番頼りにしていますか?
そして、これからどんな形の「安心」を目指したいでしょうか?
今日から一歩、資金管理の見直しを始めてみましょう。